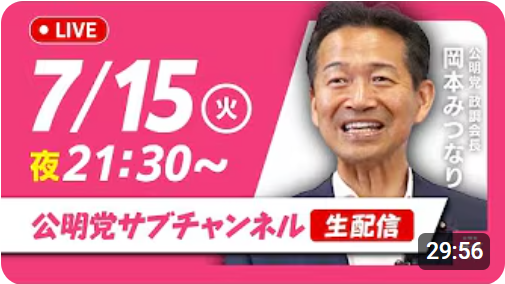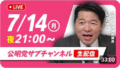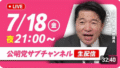まっさんのなんでもブログ【2025/7/15(火)公明党サブチャンネル生配信】の要約
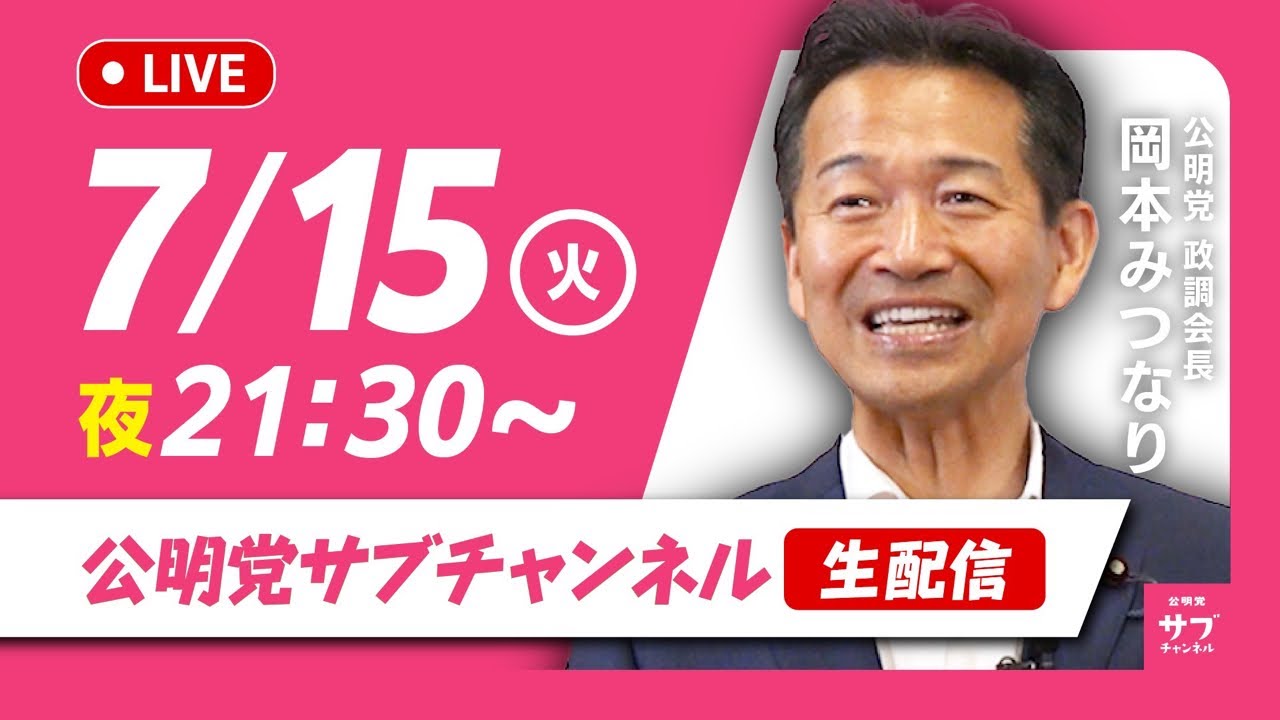
7/15(火)公明党サブチャンネルライブ配信始まります!@岡本みつなり政調会長
7/15(火)公明党サブチャンネルライブ配信始まります!@岡本みつなり政調会長
動画内容の要約です。
- 番組出演と印象
- 国際情勢と戦争観
- 平和主義の姿勢
- 平和主義と「日本人ファースト」の考え方
- 公明党の「これだけは負けない」強み
- 政策面の左右バランス
- 年少扶養控除とは?
- 減税への姿勢
- 引きこもり支援に対する公明党の考え
- 政策の方向性
- 派遣社員の賃金アップに対する公明党の方針
- 政策立案アンケート「We connect」アンケートによる政策形成
- 賃金の「額面」を重視
- 官民60兆円の投資で支援
- 公的賃金の引き上げ
- 政策の目的
- 地方自治体の基金運用について
- ソブリン・ウェルス・ファンドとの違いとリスク管理
- GPIFの成功事例と応用
- 公明党の政策的な位置づけ
- 働き方改革の再構築に向けて
- 個人に合った柔軟な働き方
- 改革の本来の目的とズレの問題
- 今後の方向性
番組出演と印象
- BS日テレ「深層ニュース」にて、維新の会の青柳氏、参政党の神谷氏とともに出演。
- 青柳氏は元国連職員という経歴を活かし、事実ベースの説明が分かりやすかったと評価。
- 神谷氏は党代表としてのアピール力・ブランディング力が際立っており、政党支持が本人に集約されている現状を指摘。
国際情勢と戦争観
- イランへの米国の攻撃によって戦争が終結したとの主張に対して、公明党の立場としては懐疑的。
- 「広島・長崎の原爆投下は必要だった」とする歴史認識には納得できないと明言。
- 戦争の早期終結は望むものの、大規模攻撃を手段として正当化する考えには賛同できない。
平和主義の姿勢
- 「戦争・核反対」「日本人ファースト」の考えは理解しつつも、それを実現する方法として武力や経済制裁は避けるべきと強調。
- 日本人の生活や命を守るためには他国との協調や信頼関係の構築が必要であるとの見解。
平和主義と「日本人ファースト」の考え方
- 戦争・核反対の姿勢を明確にし、平和主義に強く共感。
- 「日本人ファースト」という考え方は国会議員として当然理解しているが、その実現手段として戦争や経済制裁といった強硬手段は支持できない。
- 日本人の生活や命を守るには、他国との友好関係や協調が重要。
- 国内優先の政策を掲げつつも、グローバルな視点でバランスの取れた外交や政策形成が必要と強調。
公明党の「これだけは負けない」強み
- 基本的価値観の違い:他党との最大の違いは、政治の中心に「人間の生命・生活・尊厳」を置く価値観にある。
- 中道政治の哲学:
- 単なる「右と左の中間」ではなく、独立した「中道という思想・価値観」。
- “中道”は「道に当たる」という意味であり、その道とは「平和・人権・自由・民主主義」。
- この哲学をもとに、政策をぶれずに形成している点が特長。
政策面の左右バランス
- 安全保障では「右寄り」に見えることがあるが、日本人の命を守る目的に基づくもの。
- 社会保障では「左寄り」に見えるが、個人の生活支援のために必要な姿勢。
- こうしたバランスも中道政治の一環であり、右左の寄り方は目的に応じた戦略的判断。
年少扶養控除とは?
- 子どもがいる家庭の支出負担を軽減するため、所得から控除される制度。
- 民主党政権時代に廃止されたが、子育て支援の観点から公明党は再導入を目指している。
(時間がかかる理由)
- 他の控除制度(例:103万円の壁 → 160万円への引き上げ)など、段階的な税制調整が先行している。
- 年少扶養控除は復活の議論が進められているが、税制改正の枠組みや政党間の合意形成に時間が必要。
- また、公明党としては所得税控除を通じて99%以上の就労者が減税を受けられる枠組みをまず整備したいという順序。
減税への姿勢
- 公明党は「減税推進政党」として、年少扶養控除だけでなく奨学金減税や課税控除拡大なども同時に議論。
- 所得税を軽減することで、可処分所得(使えるお金)を増やし、生活のゆとりを確保する方針。
- 「給料の額面を上げる+控除拡大」のセットで国民の生活を守ると主張。
引きこもり支援に対する公明党の考え
- リーダー的存在の下野太氏(元教師)が党内でプロジェクトを牽引し、政府にも積極的に提案。
- 若年層から高齢層まで広範な対象者を想定。引きこもりの背景や状況は多様であるとの認識。
- 支援にあたっては「一人ひとりに寄り添う」ことが中心。無理に外へ出すような対応は持続可能ではなく、丁寧で個別的な支援が必要。
(家族単位でのアプローチ)
- 本人のみならず、ご家族も大きな悩みや負担を抱えているという点に注目。
- 支援は「家族全体を対象にした制度設計」にも広げ、行政の仕組みとして体制化を進める方針。
政策の方向性
- 行政サービスとして個別対応を可能にする仕組みの整備と制度設計を政府に提案済み。
- 持続可能で柔軟な支援を目指し、**「押し出す支援」ではなく「寄り添う支援」**という哲学が貫かれている。
派遣社員の賃金アップに対する公明党の方針
- 基本姿勢:すべての働く人を「正社員待遇」で応援する社会を目指す。
- 働き方の多様性は尊重しつつ、待遇格差はなくしていくべきとの立場。
- 非正規・派遣で働く方にも正社員並みの待遇を推進。
政策立案アンケート「We connect」アンケートによる政策形成
- スマホで実施された政策立案アンケートには約13万人が参加。
- 回答をAIで分類し、公約に反映。多くの生活者の声が反映されたことを強調。
賃金の「額面」を重視
- 給与の額面(表面の支給額)が上がれば、将来的な年金額も増える。
- 賃金が上がることで「希望」が生まれ、持続可能な暮らしにつながると強調。
官民60兆円の投資で支援
- 今後5年間で中小企業を中心に60兆円規模の官民投資を計画。
- 設備投資、研究開発、DX(デジタルトランスフォーメーション)、人材投資などが対象。
- 目的は「企業が儲ける」ことではなく、その利益を働く人へ分配する仕組みづくり。
公的賃金の引き上げ
- 民間賃金引き上げを促す前提として、まず行政が関与できる賃金(保育・介護・医療など)を底上げ。
- 「エッセンシャルワーカー」の待遇改善は政治の責任として進める。
政策の目的
- 物価上昇を上回る継続的な賃金アップを実現し、働く人の生活を守る。
- 派遣社員や非正規雇用者を含め、誰ひとり取り残さない賃上げ政策を目指している。
地方自治体の基金運用について
- 自治体が保有する「減債基金」は将来の債務返済のための積立で、債券中心に運用されている(国債や地方債)。
- 金利上昇により債券の時価評価が下がり、含み損が発生する(例:100で買った債券が金利上昇で90に評価される)。
- 含み損が出ていても、売却しない限り実損ではないが、運用・活用の自由度が減る。
ソブリン・ウェルス・ファンドとの違いとリスク管理
- 公明党が提案する政府系ファンド(ソブリン・ウェルス・ファンド)は、
- 国が保有する資産を国民のために運用し、
- 得られる収益を政策財源に活用するという枠組み。
- 基本思想:リスク最小化 × リターン最大化
リスクヘッジの具体策
| 方法 | 説明 |
| アセット・アロケーション | 資産を複数の種類(株式・債券・国内・国外など)に分散し、変動リスクを緩和 |
| シャープ・レシオ最適化 | 同じリスクなら高いリターン、同じリターンなら低いリスクを目指す効率的運用 |
| キャッシュフロー重視 | 売買益ではなく、配当金や債券の利息収入を主な収益源とする安定的運用 |
GPIFの成功事例と応用
- 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は250兆円を運用中。
- 分散投資によってリスクを低減し、運用効率を向上。
- リスク管理システムは世界最高水準との評価。
- 売買益よりも配当・利息で4兆円以上の収入を毎年獲得している。
公明党の政策的な位置づけ
- ソブリン・ウェルス・ファンドはすでに政府が「骨太方針2025」で検討を明記。
- 公明党はこの仕組みを推進し、持続可能な政策財源を目指す提案政党。
- 運用益を社会保障や未来投資に回すというビジョンも提示。
働き方改革の再構築に向けて
- 健康的に働くことは改革の大前提。働くことで健康を害するなら本末転倒。
- 公明党の公約作成時にも、同様の声が多数寄せられた(Vコネクトアンケートでも確認済み)。
個人に合った柔軟な働き方
- 会社主体ではなく、働く個人が自分で選べる働き方が大切。
- ただし、医療的・法的観点から健康を守る仕組みは国が管理すべき。
- 収入が大きく下がるような改革は本末転倒であり、「所得向上」が改革の目的と強調。
改革の本来の目的とズレの問題
- 働き方改革は「生産性向上と所得増」を目的として始まった。
- 欧米では労働時間が短く、生産性と給与が高い傾向がある。
- 日本でもそれを踏まえて労働時間短縮が導入されたが、手段が目的化し、結果として給与低下や働きづらさを招いているとの懸念。
今後の方向性
- 一人ひとりの多様な働き方に対応できる制度設計が必要。
- 健康を維持しながら、自分らしい働き方が選べる社会を目指す。
- 政策としては、「労働時間短縮=賃金低下」という誤解を正しつつ、賃金水準を保ち、やる気と安心を両立する働き方改革へ転換する。